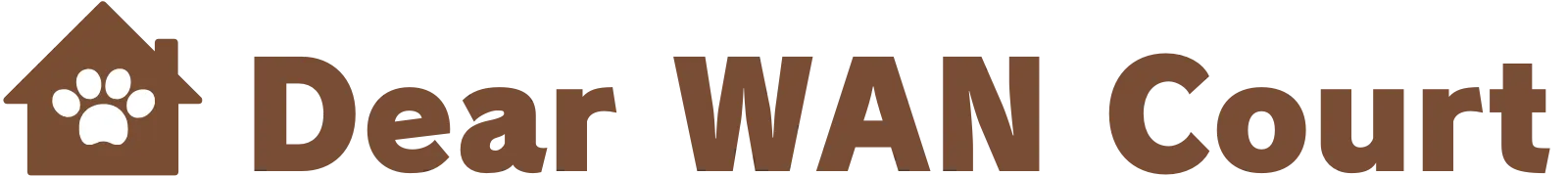
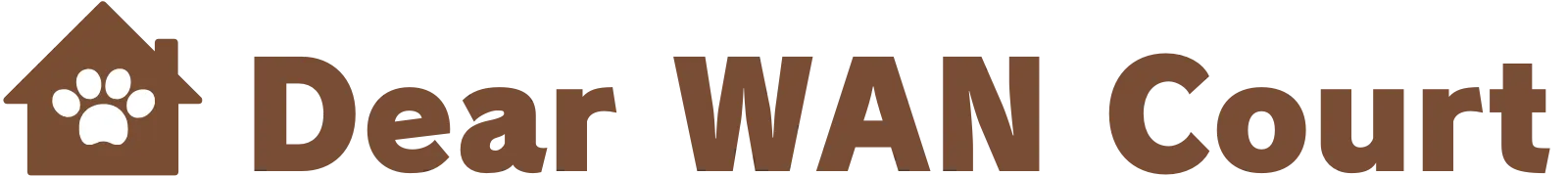
2025年10月06日
2025年10月06日

小林 まいこ
獣医師・動物ライター
愛犬との生活で不可欠となる「狂犬病ワクチン」。
法律によって年に一度の接種が義務付けられており、愛犬のためだけでなく、社会全体を守るためにも必ず接種する必要があります。
しかし、「いつ、どこで、いくらで受けられるの?」「副作用が起きたらどうしよう…」といった不安や疑問を持つ飼い主さんも少なくありません。
この記事では、そんな飼い主さんの疑問や不安を解消するために、狂犬病の基本的な知識から、具体的な費用、接種後の注意点までを解説します。

狂犬病ワクチンは、毎年接種する必要があります。その背景には、狂犬病という病気の恐ろしさと、私たちの社会を守るための法律上の義務が存在します。
ここでは、ワクチン接種が必要な理由を3つのポイントから詳しく見ていきましょう。
狂犬病は、狂犬病ウイルスによって引き起こされ、ワンちゃんだけでなく人を含むすべての哺乳類に感染する可能性のあるウイルス性の人獣共通感染症です。
この病気の最も恐ろしいところは、一度発症してしまうと有効な治療法が存在せず、致死率がほぼ100%である点です。
感染した動物は興奮状態や攻撃性の増加、ふらつきや麻痺などの症状が見られ、やがて呼吸困難により死亡します。
幸い、現在の日本国内で狂犬病の発生はありません。しかし、世界に目を向けると、今なお年間数万人が命を落としており、非常に恐ろしい感染症なのです。
※参考:狂犬病(厚生労働省)
狂犬病の主な感染経路は、ウイルスを含む唾液を介した咬み傷です。
咬み傷だけではなく、傷口および目や口の粘膜を舐められたり、ウイルスの付着した爪で引っ掻かれても感染する可能性はあります。
体内に侵入したウイルスは、神経を伝って脳へと達して発症します。
感染はワンちゃん同士に限りません。感染した動物に人が咬まれれば、人も同様に感染するリスクがあります。
現在、日本は発生がない清浄国とされていますが、日本を取り巻く世界のほとんどの地域で狂犬病の発生が認められています。
また、海外ではキツネ、アライグマ、コウモリなどの野生動物からの感染も多く報告されています。
日本においても万一ウイルスが侵入すれば、流行するリスクが高いといえるでしょう。
社会全体を守るためにも、愛犬へのワクチン接種が不可欠です。
恐ろしい狂犬病のまん延を防ぐため、日本で定められた法律が「狂犬病予防法」です。
この法律では、ワンちゃんの飼い主に登録、狂犬病予防注射の実施、犬鑑札・注射済票の装着が義務付けられています。
生後91日を超えたすべてのワンちゃんは、年1回の予防注射が必ず必要です。ワクチンを接種すると、その証明として「注射済票」が交付されます。
また、ワンちゃんを飼い始めた際には、犬を取得した日(生後90日以内の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の所在地を管轄する市区町村長への登録が義務付けられており、登録の証明として「鑑札」も交付されます。
鑑札や注射済票は愛犬に装着し、常に携帯することが求められています。
ただし、令和4年6月1日からは、あらかじめ環境大臣にマイクロチップ登録情報の通知の求めを行なった市区町村に所在するワンちゃんは、そのマイクロチップ情報の登録が狂犬病予防法に基づく犬の登録とみなされるようになりました。
この制度によって、ワクチン接種の有無を明確にし、多くのワンちゃんが狂犬病ワクチンを接種することで、社会全体で狂犬病のまん延を防止する体制が整えられているのです。
※参考:狂犬病予防法(農林水産省)

予防注射の必要性は理解していても、いざ愛犬に受けさせるとなると「どこで接種できるの?」「費用はどのくらい?」と、たくさんの疑問が浮かんでくるかもしれません。
ここでは、具体的な接種時期や費用、手続きについて解説します。
狂犬病ワクチンの接種スケジュールは、以下のとおりです。
ワンちゃんが生まれてから91日(約3ヵ月)が経ったら、最初の予防注射を受けさせます。
初回の接種を終えた後は、狂犬病に対する免疫を維持するために、年に1回、継続して追加接種を受けなければなりません。
一般的には、多くの自治体で毎年4月〜6月を「狂犬病予防注射月間」と定めており、この期間に公園や公民館などで集合注射が実施されます。
集合注射の案内は、各市区町村で犬の登録台帳に基づいて飼い主さん宛に3月下旬ごろに送られてきます。
4~6月以外でも、動物病院であれば年間を通じていつでも接種可能です。
狂犬病ワクチンの接種にかかる費用は、各自治体や動物病院によって異なります。
動物病院で接種する場合、診察料などが別途必要になるケースもあるため、集団接種会場より高額になることがあります。
また、これらの費用に加えて、初めて登録する際には「鑑札交付手数料」、毎年狂犬病ワクチンを接種するごとに「注射済票交付手数料」が別途必要になる場合があります。
それぞれの費用は、500円〜1,000円程度のケースがほとんどでしょう。
狂犬病ワクチンの接種と同時に、犬の登録と注射済票の交付手続きを行わなければなりません。
犬の登録は、生後91日以上のワンちゃんを飼育し始めた際に行う手続きです。住んでいる市区町村に、愛犬の情報や飼い主さんの情報などを登録します。
手続きすると、「鑑札(かんさつ)」という金属製のプレートが交付されます。これは、愛犬にとっての「戸籍」のようなもので、生涯に一度きりの登録です。
令和4年6月1日以降、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムへの登録が義務となり、この登録が狂犬病予防法に基づく犬の登録として認められています。
そのため、マイクロチップを登録していれば、従来の鑑札を受け取る必要はありません。
一方、「注射済票」は、狂犬病ワクチンを接種したことを証明するものです。
住んでいる自治体の集団接種会場や動物病院で予防接種をした場合、その場で発行されることが多く、手続きは不要です。
ただし、住んでいる自治体以外の病院でワクチンを接種した場合は、「予防接種証明書」のみ発行されます。その場合は証明書を受け取り、役所で注射済票を発行してもらう必要があります。
狂犬病ワクチンは動物病院と自治体の集合接種会場のどちらでも受けることができますが、それぞれに特徴があります。
動物病院で接種する場合は、獣医師に健康状態をしっかりと診察してもらった上で、予防注射を受けられるのが最大のメリットです。
ほかのワンちゃんが苦手な子や持病がある子でも、個別の状況に合わせた対応をしてもらえます。
一方、集団接種会場で接種する場合は、短時間で済み、費用が比較的安いことがメリットとして挙げられます。会場に行けば、問診票の記入と簡単な視診だけでスムーズに接種が進みます。
飼い主さんのライフスタイルや愛犬の性格に合わせて接種場所を選びましょう。

愛犬の健康を守るための狂犬病ワクチンですが、人間のワクチンと同様に、接種後に副反応が起こる可能性もゼロではありません。
しかし、事前に副反応について理解し、正しい対処法を知っておけば、落ち着いて対応することができます。
ここでは、ワクチン接種後に起こりうる副反応や、接種後の注意点などを見ていきましょう。
狂犬病ワクチンは、体の中に免疫を作るために、ウイルスを死滅させて感染能力を失わせたものから作られているため、副反応は起こりにくいとされています。
しかし体の免疫システムが反応する過程で、副反応が見られることがあります。とくに気をつけたいのは、「アナフィラキシーショック」です。
アナフィラキシーショックとは命の危険がある重篤な副反応で、接種後30分以内にぐったりする、呼吸が速くなる、嘔吐、けいれんといった症状が現れます。
命に関わる危険な状態のため、すぐに動物病院での処置が必要です。
また、ほかにも一時的に以下のような症状が見られることがあります。
これらの症状は、通常、接種後数時間から3日以内に起こります。
とくに、注射部位の腫れや顔のむくみ、下痢に関しては治療が必要になるケースもあるため、病院への連絡と受診が必要です。
症状が軽度であっても、心配な様子であれば獣医師に相談しましょう。
万が一に備え、接種後はしばらく院内や病院の近くで様子を見て、帰宅後も注意深く愛犬の様子を観察することが大切です。
ワクチン接種後の愛犬の体は、免疫を作るために頑張っている状態です。体に大きな負担をかけないように当日はできるだけ安静に過ごしましょう。
ワクチン接種当日は、ドッグランで走ったり長時間お散歩したりなどの激しい運動を避けます。
また、シャンプーやトリミングも体力を消耗させる可能性が高いため、接種当日は控えたほうがよいでしょう。
「食欲はあるか」「ぐったりしていないか」など、愛犬の様子をこまめにチェックすることも大切です。
もし、少しでもいつもと違うと感じることがあれば、すぐに動物病院へ連絡しましょう。
シニア犬で体力が著しく低下している場合や、心臓病、腎臓病、てんかんなどの慢性的な持病がある場合などは、獣医師がワクチン接種によるリスクが高いと判断することがあります。
健康上の理由でワクチン接種が難しいと診断された場合は、無理に接種する必要はありません。
その際、獣医師に相談すると「狂犬病予防注射実施猶予証明書」という書類が発行されます。
証明書を受け取り、お住まいの市区町村の役所で手続きすると、その年度のワクチン接種義務が免除されます。
これはあくまでも「接種の免除」ではなく「猶予」の措置です。翌年以降、体調が回復すれば接種を検討することになります。
※参考:狂犬病集合予防注射実施のためのガイドライン(社団法人 日本獣医師会)
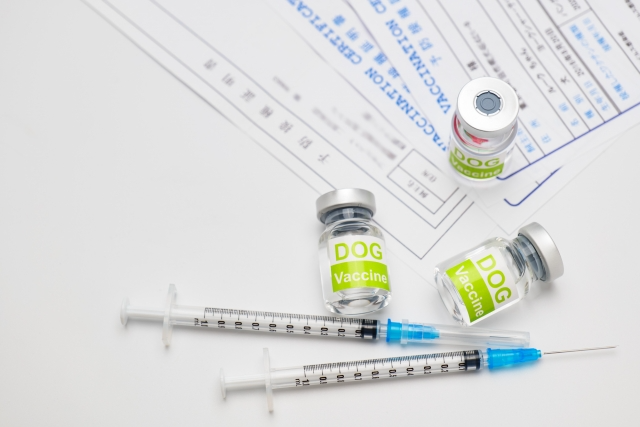
狂犬病ワクチンについて、混合ワクチンとの違いや接種を忘れた場合など、さまざまな疑問を持つ飼い主さんもいるでしょう。
ここでは、狂犬病ワクチンに関するよくある疑問に回答します。
予防できる病気の種類と、法律上の義務かどうかが大きな違いです。
狂犬病ワクチンが「狂犬病」という一つの病気だけを予防するのに対し、混合ワクチンは「犬ジステンパー」や「犬パルボウイルス感染症」など、ワンちゃんがかかりやすい複数の感染症をまとめて予防するためのワクチンです。
また、狂犬病ワクチンは「狂犬病予防法」によってすべてのワンちゃんに接種が義務付けられています。
一方で、混合ワクチンは任意接種となっており、飼い主さんの判断で接種します。
体に負担をかける可能性があるため、一般的には同時接種は推奨されていません。
狂犬病ワクチンと混合ワクチンは、それぞれ異なる種類の病原体から作られています。同時に接種すると、ワンちゃんの体に大きな負担がかかり、リスクが高くなるでしょう。
そのため、多くの動物病院では、どちらかのワクチンを接種してから2週間〜1ヵ月程度の間隔を空けるのをおすすめしています。
ただし、飼い主さんの事情やワンちゃんの健康状態によっては、接種スケジュールを調整する場合もあるので、かかりつけの獣医師とよく相談してください。
飼い主は保健所への届け出が義務付けられており、愛犬は狂犬病の疑いがないか獣医師による検診を受ける必要があります。
万が一、愛犬が人を噛んでしまった場合、飼い主さんは「狂犬病予防法」に基づき、事故から24時間以内にその旨を保健所に届け出なければなりません。
その後、噛んだワンちゃんが狂犬病にかかっていないかを確認するため、最低2回以上の獣医師による検診が義務付けられます。
※参考:飼い犬が人を咬んだ場合の手続きについて(厚生労働省)
狂犬病ワクチンを接種しない場合、法律違反となり20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
狂犬病ワクチンの接種は法律で定められた飼い主さんの義務です。接種を怠ることは「狂犬病予防法」違反にあたり、法的なペナルティを受ける可能性があります。
うっかり忘れてしまった場合は、気付いた時点ですぐに動物病院で接種を受けましょう。
病気や高齢などの理由で接種が難しい場合は、必ず獣医師に相談し、「注射猶予証明書」を発行してもらい、自治体に届け出る必要があります。
室内犬であっても法律上の義務であるため、必ず狂犬病ワクチンの接種が必要です。
「ずっと家の中にいるから大丈夫」と思うかもしれませんが、狂犬病ワクチンの接種義務は、飼育場所に関係なく、すべてのワンちゃんが対象です。
室内で飼育している愛犬でも、玄関のドアを開けた瞬間に脱走してしまったり、散歩や災害時の避難所で他の動物と接触したりと、予期せぬ形で感染動物と接触する可能性はゼロではありません。
日本に狂犬病が侵入した場合のまん延を防ぐためにも、室内犬でも必ずワクチンを接種しましょう。
ドッグランやペットホテル、愛犬と宿泊できるホテルなどで接種証明書の提示を求められることがあります。
多くの施設では、ほかの利用者の安全を守るため、証明書の提示をルール化しています。
愛犬とのお出かけを楽しむためにも、証明書は大切に保管し、いつでも提示できるようにしておきましょう。