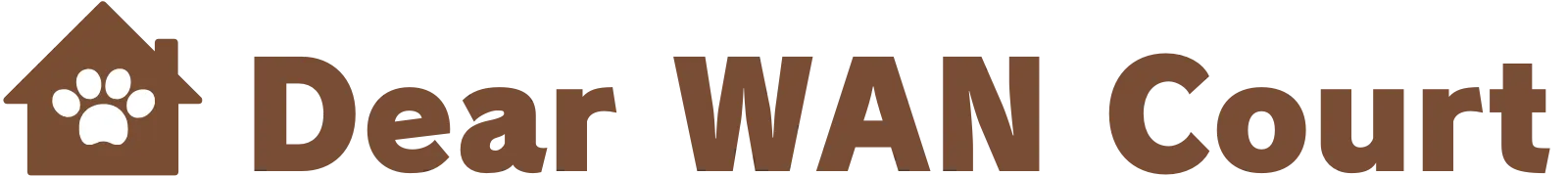
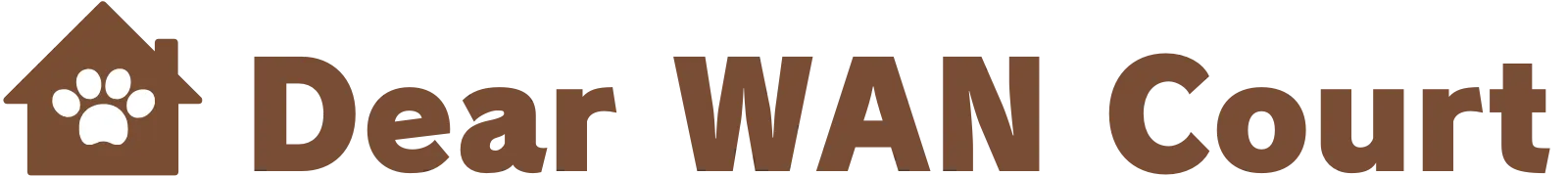
2025年07月21日
2025年07月21日

さかもと はるか
ペットライター、愛玩動物飼養管理士2級、JKC公認トリマーライセンスC級
「ハーネスの種類が多すぎて愛犬に合うものがわからない」「そもそも首輪と比べてどちらがいいの?」と悩んでいる飼い主さんもいるのではないでしょうか。
ハーネス(胴輪)は形状・素材ともに種類が豊富で、愛犬にぴったりのものを選ぶのは難しいものです。
この記事では、犬用ハーネスの選び方を解説。首輪との違い・サイズの測り方・犬種別おすすめタイプ・安全に使うコツまで詳しくご紹介します。
愛犬にぴったりの一本を見つけて、毎日のお散歩をもっと安全で快適な時間にしましょう。

ハーネスは、ワンちゃんの胴体に装着する道具で、リードを取り付けて散歩やお出かけの際に使用します。リードを取り付けることで動きを制御し、ワンちゃん自身や身の回りの安全を守る役割があります。
ハーネスは、もともと犬ぞりやウェイトプルなどの競技で使用されてきました。
重い物を牽引する際に、ワンちゃんの体に負担がかかりにくいように作られており、現在では多くの飼い主さんが散歩時にハーネスを利用しています。
実際に、株式会社ピクシーが実施したアンケートによると、ハーネスを使用している方の割合は全体の44%という結果になりました。
首輪を使用しているのは39%なので、ハーネスの利用者が多いことがわかります。
※参考:PR TIMES「犬に使っているのは首輪?それともハーネス?首に負担がかからないのはどっち?:『ペット保険比較のピクシー』」

首輪との大きな違いは、装着する場所です。
首輪はワンちゃんの首に装着するのに比べ、ハーネスはワンちゃんの胸やお腹などの胴体に装着します。そのため、愛犬が散歩中に引っ張っても、首に負担をかけにくいアイテムといえるでしょう。
ただし、ハーネスにはメリットだけでなく、デメリットもいくつかあります。ここからは、ハーネスと首輪、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
| 項目 | ハーネス | 首輪 |
|---|---|---|
| 首・気管への負担 | 分散しやすい(負担軽減) | リードの力が首に集中しやすい |
| コントロール/しつけ | 力が分散するため首輪より合図が伝わりにくい。前胸クリップ型は引っ張り対策に活用可。 | 合図がダイレクトで基本トレーニングに使いやすい |
| 着脱の手間 | 身体を通すため慣れが必要な犬も | 巻いてバックル留めで簡単 |
| 抜けリスク | サイズ次第で低減可能 | 頭が小さい犬種等は抜けやすい場合 |
| シニア・気管虚脱 | 適する(圧分散) | 不向きの場合あり |
ハーネスには首への負担が少ないなどのメリットがある一方で、しつけには不向きといったデメリットもあります。主な特徴は以下の通りです。
メリット
デメリット
ハーネスの一番のメリットは、首に負担をかけにくいことです。上半身全体に装着するような作りになっているため、引っ張っても負荷が分散され、体に負担がかかりにくい構造です。
ただし、ハーネスは装着する範囲が広いため、ワンちゃんによっては付けるのを嫌がる場合があります。また、負荷が分散されるため、しつけに向いていない点もデメリットとして挙げられます。
続いて、首輪のメリット・デメリットを見ていきましょう。
メリット
デメリット
首輪は、1本のベルトを愛犬の首に巻きつけるような構造になっているため、ハーネスに比べて着脱しやすい点がメリットです。リードの動きが愛犬に伝わりやすく、しつけにも適しています。
ただし、引っ張り癖がある場合、首に負担がかかる可能性があります。長時間装着していると、皮膚トラブルを引き起こすこともあるのがデメリットといえるでしょう。
愛犬に合うものを選ぶには、愛犬の年齢や性格、体格などに合わせて選ぶとよいでしょう。
ハーネスと首輪、それぞれに適しているワンちゃんの特徴は以下のとおりです。
ハーネス
首輪
ハーネスと首輪どちらかを選ぶ際には、両方試してみて愛犬に合ったものを選ぶことが理想です。愛犬が安全に楽しく散歩できるほうを選びましょう。

愛犬にとって快適で安全なハーネスを選ぶには、「サイズ」「形状」「素材」の3点を軸に検討することが大切です。
犬種や体格、性格によって適したタイプは異なるため、それぞれの特徴を理解してから選ぶようにしましょう。
ここからは、愛犬にぴったりなハーネスを選ぶ方法を詳しく解説します。
ハーネス選びで最も重要なのは、サイズです。
正しいサイズのハーネスを選ばないと、体に負担がかかったり、すり抜けたりする恐れがあります。ハーネスの購入前には、必ず愛犬の体のサイズを測りましょう。
サイズ選びでは「首回り」「胴回り(胸囲)」「体重」の3点を基準にします。測定はメジャーを使い、体より指1本程度の幅をとったうえで、ぴったりフィットする長さを確認してみてください。
メーカーによってハーネスのサイズ感が異なります。そのため、商品ごとのサイズ表を必ずチェックしてから購入しましょう。
ハーネスの代表的な形状には、以下のような種類があります。
H型は安定性が高く初心者にも扱いやすい設計です。ベスト型は洋服のように着用でき、デザイン性とフィット感を兼ね備えています。
8の字型はワンちゃんの足を持ち上げずに装着できるものが多く、着脱しやすい点が特徴です。
イージーウォークハーネスは、胸元部分にリードを付ける部分があるハーネスです。愛犬が前に引っ張ると体が反転してしまう仕組みになっており、引っ張り防止に適しています。
愛犬の性格に合わせて使いやすい形状のハーネスを選んでみてください。
素材もハーネスを選ぶうえで重要な要素の1つです。ハーネスの素材の一例を紹介します。
メッシュ素材は通気性が良く、夏場や蒸れやすい愛犬に最適です。クッション素材は皮膚や毛への摩擦を軽減し、長時間の着用にも向いています。
ナイロン製は軽量で汚れにも強く、日常使いに便利。おしゃれで高級感のあるデザインを求めている方には、合皮のハーネスがおすすめです。

ここからは、ワンちゃんのタイプに合わせておすすめのハーネスの特徴を紹介します。
小型犬は体が華奢で引っ張る力も強くないため、軽量で体にフィットするハーネスがおすすめです。
特にベスト型やソフト素材を使用したタイプは、着け心地が良く、体への負担も少ないのが特徴です。
小型犬はハーネスが抜けてしまうリスクも高いため、調整ベルトでしっかりと固定できて脱げにくい構造のものを選ぶとよいでしょう。
中型犬には、動きやすさと安定感のバランスが取れたハーネスが適しています。
活発に動く犬種も多いため、肩や胸にしっかりとフィットするH型タイプがおすすめです。サイズ調整がしやすいタイプを選ぶと、体型の変化にも対応しやすくなります。
大型犬には、飼い主さんがしっかりとコントロールでき、強い力にも耐えられるようなホールド力と耐久性に優れたハーネスが必要です。
肩と胸を包み込むような構造のものが望ましく、強度のあるナイロンやパッド入りの素材などがよいでしょう。
引っ張り癖がある場合は、前側にもリードを付けられるイージーウォークハーネスも効果的です。力が強いため、安全性と制御性を両立できるものを選びましょう。
フレンチブルドッグやパグなどの短頭種は気道が狭く、首への負担が大きい首輪は不向きです。そのため、胸部にしっかりとフィットし、圧力を分散できるベスト型ハーネスがおすすめです。
やわらかい素材やクッション性のあるタイプを選ぶと、呼吸を妨げず快適に使用できます。また、体型に個体差があるため、細かく調整できるモデルを選ぶことも大切です。

ハーネスは愛犬の安全を守る重要なアイテムですが、使い方を誤ると思わぬ事故につながる可能性があります。事故を防ぐためにも、ハーネスの正しい使い方を知っておくことが重要です。
ここでは、ハーネスを使う際の4つの注意点を解説します。
ハーネスは、ただ着ければいいというものではなく、正しい装着位置と締め具合がとても大切です。
肩や胸を圧迫しないように調整し、ハーネスとワンちゃんの体の間に指が2本入る程度のゆとりがあるのが理想です。
特に前足の付け根部分がこすれると皮膚トラブルの原因になるため、フィット感と可動域を確認しましょう。
装着後は必ず歩行やジャンプに支障がないか観察してみてください。正しくハーネスを装着すると、思わぬ脱走や事故を防げます。
安全性や快適性を高めるために、愛犬に合ったサイズのハーネスを使用しましょう。
ハーネスが大きすぎると脱げやすくなり、散歩中の逃走や事故につながるリスクがあります。一方で、きつすぎると皮膚が擦れたり、呼吸や血流に悪影響を及ぼしたりする危険性もあるでしょう。
購入前には必ず胴回りや首回りを測定し、体型に合ったサイズを選びます。定期的にサイズを見直し、体型の変化に応じて適切に調整・交換することも忘れないようにしましょう。
ハーネスを嫌がる愛犬に無理やり装着すると、ハーネスへの拒否反応が強くなってしまい、装着時に暴れたりストレスが蓄積される場合があります。
ハーネスに慣れてもらうには、まず室内でハーネスを見せて、おやつなどで「よい印象」を与えることから始めましょう。その後は短時間だけ装着し、少しずつ時間を延ばして慣らしていきます。
慣れるまで数日〜数週間かかる場合もあるため、焦らず愛犬のペースに合わせて慣らしていくことが大切です。
ハーネスは消耗品であるため、長期間使用すると素材の劣化や金具のゆるみ、縫製のほつれが起こりやすくなります。
見た目には問題がなくても、強度が落ちている可能性もあり、定期的なチェックが必要です。特に毎日のように散歩で使用している場合は、半年〜1年程度を目安に買い替えを検討するとよいでしょう。
また、雨や汚れで洗濯を繰り返すと、素材が傷んでフィット感が悪くなることもあります。安全な散歩を続けるためには、壊れる前に予防的な買い替えを意識しましょう。