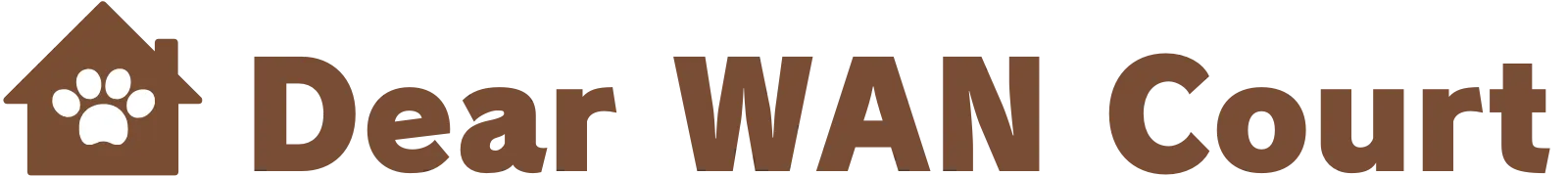
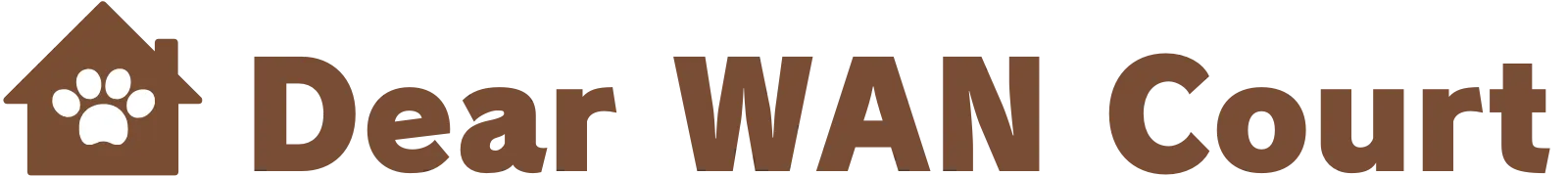
2025年05月31日
2025年06月27日

小林 まいこ
獣医師・動物ライター
犬の皮膚病は、さまざまな種類が存在し、動物病院でも多く相談されています。アレルギーや何かの細菌に感染したり、カビやダニなどが原因の場合もあるようです。
犬は自分の症状を説明したり、飼い主に状態を報告することができません。飼い主が症状などを理解し、対応していくことがとても大切です。
かゆみ、できもの、脱毛など、犬の皮膚トラブルはとても多くありますので、重大な病気が隠れていないか、しっかりとチェックしましょう。
犬は人間に比べて薄く、デリケートな皮膚を持っています。そのため、皮膚トラブルが起きやすいと言われているため、飼い主のケアや早期発見が重要です。
皮膚病の原因などを事前に知っておくことで、予防に役立ちます。もしかしたら愛犬も皮膚トラブルになっているかもしれない、と思った人は、早めに対応しましょう。
皮膚病は人間にも発生しますが、犬の場合は自分の状態を伝えたり、説明したりすることができません。以下のような症状がよくある症状としてあげられますので、確認してみてください。
さまざまな原因が考えられますが、このような症状を発見した場合は、早急に動物病院へ相談しましょう。
ここでは、皮膚病の原因となることを説明します。人間と似ているような原因もありますので、愛犬の皮膚病原因はなんであるのか、しっかり考えてみてください。
人間と同じように、犬も花粉、食物、ハウスダスト、紫外線など、免疫機能が過剰に反応して、かゆみや赤みが出てしまいます。
アレルギーの場合は、完治が難しいため、できる限り症状が少なくなるよう、動物病院に相談するなどしていきましょう。
細菌、真菌にはブドウ球菌やマラセチア菌など、犬の皮膚にもとから存在している「常在菌」と皮膚糸状菌などのように外部から侵入した菌があります。
皮膚バリア機能や免疫機能が働いている場合は、大きなトラブルには発展しません。
犬のストレス要因は、運動不足、引越しや家族の仕事などの生活環境の変化、別のペットとの関係性など、さまざまなものです。
ストレスが引き起こす自律神経の乱れは、免疫力を低下させ、皮膚トラブルを発生させてしまいます。
ストレスを和らげようと、執拗に舐めてしまったりすることで、脱毛や炎症を起こしてしまうケースなど、悪循環も少なくありません。
ノミ、シラミ、ヒゼンダニ、毛包虫、マダニなどが原因となり、かゆみをともなって皮膚トラブルになります。
また、害虫などがトラブルを引き起こすことがありますので、散歩の途中、外出時、庭などで遊んでいる時なども注意が必要です。
季節の変化により、気温が高かったり、湿度が高い環境など、皮膚に細菌が繁殖しやすいケースがあります。
また、湿度が低すぎて乾燥してしまう状態も、皮膚病を起こしてしまう原因です。乾燥した場所では、皮膚の水分がなくなってしまい、バリア機能が低下します。
ここでは、犬がかかりやすいよくある皮膚病について説明します。
それぞれ原因が違い、さまざまな症状がありますので、しっかり確認してください。
過剰なアレルギー反応の結果、皮膚炎につながっているものです。
生後半年~3歳くらいまでの若い時期に発症し、顔や耳、足先、脇、内また、お腹、肛門周辺などに強い赤み、強いかゆみを伴います。
また脱毛、色素沈着、皮膚が厚くなるなどの状態も見られるため、個々の犬によって大きく状態が変化しますので、しっかり確認しましょう。
免疫反応によるものなので、完治は難しいのですが、できる限り症状が出ないようにコントロールしていくことが大切です。
このマラセチアという真菌(カビ)は、常在菌なので、健康な犬の皮膚にも存在します。その常在真菌が異常増殖することによって発症する皮膚病です。
発症すると、耳や口回り、あご、脇、指の間や足先、内股、肛門などにかゆみが現れ、ベタベタしたり、独特な臭いが出たりします。皮膚バリアが低下した場合に増殖するため、病気になっている犬や、免疫力の落ちた犬、他の皮膚病を発症している犬は注意が必要です。
また、湿度の高い環境や皮脂分泌が多い場合に増殖しやすい性質があるため、暖かい季節(特に梅雨時期)や皮脂のたまりやすい犬も注意が必要です。
膿皮症は、常在菌であるブドウ球菌などの細菌が、皮膚や皮膚バリア機能の異常によって、細菌が過剰に増殖することで起こる病気です。
症状として、赤い湿疹、ニキビのようなものができたり、脱毛、かゆみ、ドーナツ状のふけなどが見られます。症状が出る部位は、全身に出る可能性がありますが、特にお腹や背中、指間部、脇、鼠経部が多いようです。
膿皮症を引き起こす要因には、内分泌疾患やアレルギー疾患、ニキビダニなどの感染症、皮膚のバリア機能低下などが背景にあるため、動物病院への相談をおすすめします。
ヒゼンダニによって発症する皮膚病です。他のペットや人間にも感染しますので、注意してください。
腹部、肘、顔、耳のふちなどに、赤みや大量の固いふけが出ていたり、眠れないほどの強いかゆみが出ます。その結果、毛が抜けたり、かさぶたや皮膚がぶ厚くうろこ状になったり、元気食欲が低下することもあります。
多数のヒゼンダニの寄生によって起こる角化型疥癬と、ヒゼンダニアレルギーに反応するアレルギー型疥癬がありますが、症状や状態に大きな変わりはありません。
多くの駆虫薬は虫卵には効かず、複数回の治療が必要なため、早急に病院受診をおすすめします。
ノミアレルギー性皮膚炎は、皮膚に寄生したノミが出した唾液成分に対するアレルギー反応によって、激しい痒みや皮膚炎を起こしてしまいます。
ノミ予防をしていない犬がなりやすいため、ノミ予防をしっかり行いましょう。
ノミ感染は疥癬同様、他のペットや人にも起こりうるものです。外に出していないからと安心せず、室内でもこまめな掃除や、周囲を清潔にするなど、心がけましょう。
毛穴に寄生するニキビダニが過剰に増殖することで起こる皮膚病です。
また主に症状が出るのは、頭部、目や口の周辺、手足に発疹、痒み、赤み、脱毛などです。母犬から感染する場合や、幼犬、免疫力の下がっている病気の犬や、老犬などもかかりやすいと言われています。
皮膚の新陳代謝が短くなり、皮脂が過剰に分泌され、細胞が通常よりも早く剥がれ落ちてしまう皮膚病です。
皮膚がベタベタしたり、ふけやにおいが出たりします。この過剰な皮脂やふけは細菌や真菌が好むため、二次的にかゆみや皮膚炎も起こり、外耳炎を伴う場合があるため、早めに動物病院を受診しましょう。
特定の食べ物による過剰な免疫反応が原因で、皮膚症状や消化器症状を起こします。
嘔吐や下痢を伴い、顔や耳、手足、お腹、背中、内またなどにかゆみが出ますが、原因となる食べ物の摂取をしなければ、症状は出ないものです。
普段と違うものを食べた時や、勝手に食べてしまったなどの場合は、アレルギー症状が出ないか、注意しましょう。また、食物アレルギーは原因や症状も多岐にわたり、何がアレルゲンとなっているか難しい点も多いため、動物病院に相談してください。
犬が皮膚病になってしまった場合、どのような治療法があるのか、どのような対応が望ましいのか、飼い主として心配してしまう人もいるかもしれません。
ここでは、主な治療法について解説します。
薬用シャンプーは、皮膚をケアする成分が入っており、傷の洗浄、かゆみの軽減、抗菌、保湿、スキンケアなどさまざまな効果があります。治療や症状の軽減のために、薬用シャンプーが効果的ですが、選び方や使い方、頻度は動物病院でしっかり相談しましょう。
症状の悪化、効果がない場合など、注意する必要性があります。
薬を投与する場合は、抗生物質、抗真菌剤、ステロイド剤などの外用薬が処方される場合と、内服薬で治療する場合があります。
どちらも、飼い主がサポートしなければいけませんので、処方される時に適切な方法を、尋ねておきましょう。
食物アレルギーや免疫力の弱っている犬の場合など、療法食で症状を抑えることも検討しましょう。
アレルゲンを除去した食事や、食べやすく消化しやすいものなど、さまざまな工夫をする必要性があります。
栄養バランスがとれている療法食は、健康的な皮膚や被毛の育成に必要不可欠です。
犬の皮膚病について、状態が悪化する前に予防や早期発見が重要になります。自分では伝えることのできない犬にとって、飼い主のこまめなチェックなどはとても大切なので、ぜひ参考にしてみてください。
日常的に、犬の清潔や食事のこと、どのように過ごしているかなど、飼い主でなければわからないことはたくさんあります。
愛犬が日常的にどのように過ごしているか、皮膚病になるリスクを抱えていないか、などさまざまな視点から確認していきましょう。
虫や細菌などによる皮膚病を予防するためには、環境を整えることがとても大事です。
時期によって適切な予防薬を投与したり、生活する場所の温度や湿度管理をしましょう。こまめな掃除も重要です。
そもそも体調が悪かったり、免疫力が低下しているなどある場合は、皮膚病だけでなく他の病気が隠れている可能性もあります。
中には重大な病気になってしまう可能性もあるので、愛犬の定期的な健康チェックと動物病院の受診をしましょう。
アレルギー性の皮膚病を発症した場合、何が原因だったのか、特定する必要性があります。
その場合は、アレルギー検査や除去食試験などを行い、犬の状態をしっかり確かめてください。わからないことは動物病院へ相談し、早急に対応しましょう。